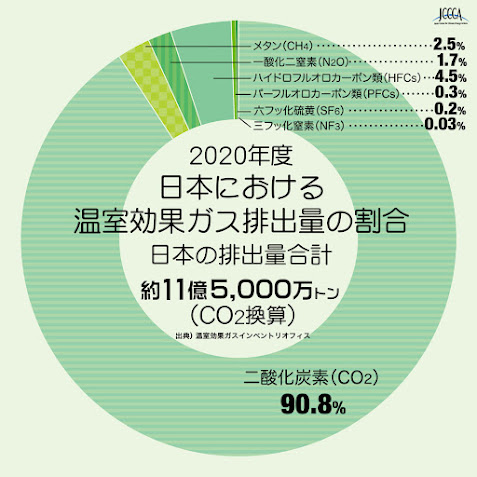上記だけではなく、化成肥料を使用した慣行農業は更に以下の問題点が指摘されています。
・人体への悪影響
その危険な化学物質を硝酸態窒素といい硝酸や硝酸イオンとも呼ばれています。海外では死亡例も出ており、厳しく規制されている国もあります。これは化成肥料に限らず有機栽培でも窒素成分肥料の与えすぎで起きることがあると報告されています。ブルーベビー症候群という赤ちゃんの病気は、窒素肥料の過剰施肥による硝酸態窒素濃度の高い食物が原因とされています。
・土壌劣化 農地の砂漠化
・害虫被害が増大
上記に示した硝酸態窒素は、逆に害虫にとっては、食料となり、栽培作物の被害となります。そのために結局、余計な農薬が必要となります。
・栄養価と味の低下
化成肥料で育った野菜や果実は、
栄養価が低いという説もあります。研究成果とかエビデンスはこの立命館大学とか複数最近では出されていますが、今後このあたりも更に証明されてくるという気がします。そして化成肥料の硝酸態窒素が過剰になると「苦み」「えぐみ」があるとも言われています。自然栽培で育った野菜、果実は、おいしく栄養価が高いというのも理解できます。
・海洋汚染
世界の沿岸水域で「デッドゾーン」と呼ばれる魚や海洋生物の全くいない海が毎年出現、毎年増えてきているようです。特にメキシコ湾に多いようですが、これも陸側で大量の化成肥料が使用され過剰な窒素、リンが下流に流出して発生するようです。
除草剤と農薬の問題
そして、除草剤のグリホサートや、殺虫剤(ネオニコチノイド)系の散布は地球環境を大きく破壊しています。そしてなによりも農業者自身の健康をも蝕んでいます。これは、もう説明の必要がないほど明確な現実です。除草剤は、ベトナム戦争時に米国が散布した枯葉剤がもとになっています。これが原因でのベトナムでの悲劇の後遺症は広く知られています。ひどい事に諸外国では禁止されているのに、日本では全く規制されていない事実があります。さらに酷いことに農協(JA)は、国が安全としているのでという理由のみで、これらをまだ平気で日本中に販売しています。自分たちが販売している製品が、国民に健康被害を与えているという事実に目を向けず、自分たちの利益を追求するだけの最低の組織に成り下がっています。農協や農林省とかの体制については、ここで書くとそれだけで膨大な闇があり1つのテーマになるので、別の機会にしますが、このままこの有害農薬の規制をしないと、日本の将来は非常に暗いものとなります。政府が動かない限り、自分自身の健康の問題は、自分自身で防御する必要があります。農薬が全て悪く、農薬全部を規制という事では無く、少なくとも現在問題となっている有害農薬を使用しているものをよく自分自身で判断する事が重要です。国、行政、政治家、厚生省、農林省、農協、マスコミを信用してはいけません。国が助けてくれないのでいるなら、自分自身が自分の頭で考え、今こそその洗脳から脱却する必要があります。日本国憲法で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められているのです。これは、憲法違反で国(農林省、農協)の犯罪ではないのでしょうか?
<除草剤散布の様子>
出典:
ハーバービジネスオンライン 参考にするブログは、マスコミはいっさい報道しませんが、いっぱいあります。
更に恐ろしい事実
更に、恐ろしいことが世界では起こっています。遺伝子組み換え、ゲノム編集してグリホサート耐性を備えた穀物(大豆、小麦、とうもろこし、、)を除草剤とセットでの販売をグローバル企業が行っています。遺伝子組み換え作物自体が、人体に影響がないのかの保証がないうえに、発がん性のあるグリホサートまみれの農作物が既にガンガン栽培されている事実があります。これを既に食料輸入大国の日本は大量に輸入しています。モルモットにされているのです。早くこの事に気づかないと今後本当に大変な事になります。
日本のスーパーに並んでいるものの60%が既にゲノム編集されているものとの情報もあります。あろうことか、遺伝子組み換えの表示義務が無くなりました。下の写真にあるように豆乳を買う場合は、「遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。」表示を確認する必要があります。何も書いてないからと安心してはいけません。
まだまだあります
<ワクチンレタス、人口肉、昆虫食、培養母乳、ゲノム編集魚>
このあたりの事は「食が壊れる」堤未果氏(文春新書)で詳しく書かれていますので、興味のある方は是非読んで見てください
自然栽培の可能性
「奇跡のリンゴ」が最近では、最も有名になっていますが、
自然栽培、
自然農法、
協成農法、
菌ちゃん農法、
リジェネラティブ農業(環境再生型農業)等、様々な形態の農法が、提案されています。これらに共通するのは、いわゆる原点回帰、化成肥料、農薬等で汚染された土壌を回復して本来の自然の中で地球古来から生息する微生物とともに農作物を栽培するという方法です。これまでの自然破壊を回復する上に、
栄養価の高い、安全な、おいしい農産物を収穫できるようになります。「奇跡のリンゴ」の結論は、
雑草です。雑草と土壌中の
微生物がキーとなっていると思います。その他の栽培方法も大体基本的に同じと思っています。
特徴としては以下
・無農薬 農薬、除草剤を使わない
・無施肥(化成肥料、合成肥料の不使用)堆肥、緑肥の活用
・不耕起栽培 豊かな土壌となる微生物との共存
そして、自然栽培の野菜や果物は、通常栽培と比較して栄養価が高いとされることが多く、その理由は栽培方法の違いにあります。自然栽培では、化学肥料や農薬を使わず、土壌の健康を重視して育てるため、作物が本来持つ栄養素を最大限に引き出します。
研究によれば、自然栽培の作物にはビタミンC、ポリフェノール、ミネラルなどの栄養素が多く含まれる傾向があります。特に、抗酸化物質であるポリフェノールの含有量は、通常栽培の作物と比べて高いことが報告されています。これは、自然栽培では作物が自然のストレスにさらされることで、より多くの抗酸化物質を生成するためです。
 |
| 奇跡のリンゴとともに木村秋則さん |
出典:
革新的リンゴ農家・木村秋則さんの自然栽培と成功までの奇跡
有機栽培の現実(無農薬)
無農薬(有機栽培)で、栽培されている農家は現在かなり増加していると思われていますが、現状では、まだまだ農家の常識は、「無農薬では無理」、「ましてや肥料無しでなんてできるわけがない」というものが本音です。昔から農業を専業で営んでいる農家は、ほとんどそう思っています。それに有機栽培、無農薬と言うと「たいへんですよね」と一般の方から言われます。「そんなことないです。農薬をかけない、雑草も刈らない分、かなり楽です。」といつも私自身は、そう思ってます。確かに有機農業での栽培農家は、全く増えない現状があるようです。2020年のデータで取り組み面積は
0.6%に過ぎません。
農林水産省が発表した「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」)においては、有機農業の面積を2050年までに100万ha(全農地の25%)へと拡大する目標が掲げられていますが、こんなもの今のままでは達成できるわけがないです。日本で有機栽培農家が増えない理由というサイトで、考察されているように有機JAS法というのが障害になっているのかもしれません。日本の事情もよくわかってない農林省の役人が海外のオーガニック規制をそのまま法律化しているのがよくわかります。
イタリアの16%、ドイツ・スペインの約10%、フランスの8.8%、韓国の2.3%等と比較しても非常に低い水準です。行政が目標だけ掲げて何の援助もしなかったらとうてい実現できるわけがない数字だというのがわからないのでしょうか?何かやっているという見せ掛けだけのハッタリです。要はやる気がないのです。この調子で上っていくとしても後30年足らずで、せいぜい3%位になったら拍手を送ります。行政は早く慣行農業からの脱却をしないと、地球環境自体が持たないという自覚が全く欠如してます。 出典:フード・マイレージ資料室
まずは、無農薬で
ですが、目標だけを掲げて何の働きかけもない行政をあてにしていては、何もできないのので、昨年は、思い切って無農薬で葡萄を栽培する事にしました。周辺の農家のどこに聞いても「それは無理。」とベテランの農家ほど言われます。それはそうです、昔からそういう指導です、教育されて、それが常識となっています。某農業指導員の人にそれが成功したと報告しても「今年は、天候が良かったですからね。」と皮肉な薄笑いをされて言われる始末です。「今年はできても来年どうなるかわからない。」とまで言われています。実をいうと、私自身も多少不安ではあります。
ジベレリン(植物性成長ホルモン)
ただ、無農薬といっても葡萄の場合、種あり品は、ほとんど市場価値がなくなってしまいます。シードレスという種類のぶどうは、もとから種がない品種ですが、あまり味がよくありません。特にシャインマスカット等最近は、皮ごと食べられるのが特徴の種類が多くなってきている現状、種があっては、売り上げが半減どころか殆どマニア受けする以外に、市場では、売れない現実があります。種を抜くためにジベレリンという植物性成長ホルモンのみは、使用します。これは、植物性の成長ホルモンなので、これが有害という事になると、果物に限らず、野菜でも植物全般ある程度自分で成長ホルモンを生成して成長を促している以上全てが有害で、人間にとって食べれないという事になります。が、有機JASでは、これが農薬登録されてしまっています。
世界的には、葡萄はワイン用として栽培されるのが殆ど(約8割がワイン用)で、日本人が発見したジベレリンというすばらしいものを理解していないのかもしれません。ここに日本の事情を知らない農林省の役人が外国からのコピーである有機JAS法の弊害が有ることを報告しておきます。有償である有機JASの認証を受けない限り「有機栽培、無農薬」をそもそもうたってはいけないのです。これを違反すると犯罪となり罰金及び懲役刑を受ける可能性が出てきます。昨年は、農林省の査察官がどこから情報を得たのか突然来園され、いろいろ調査を受けました。とりあえず有罪とはなりませんでしたが、いろいろ報告書を作成させられました。ご苦労様でした。
自然栽培農家(葡萄)
昨年(2024年)3月でしたが、
葡萄で自然栽培を実施しているという農家(ラコリーヌ)が近くにあるという事で、植え付け体験に参加させていただきました。100本のデラウェア苗木を植えるという事でした。驚きなのはその植え付け方でした。私が今まで教えてもらっ方法とは、まるで違うのです。雑草は生えっぱなしで穴を掘ってそこに植えて添え木を立てるだけ、施肥は全くしません。少し周りにマルチがあるのみでした。主催者の方に、「これで植えた苗木はどれくらいの率でつきますか?」と質問すると「80%はつきますよ」との回答でした。驚異の数字です。従来の私の苗木の植え方は、お手本通りで、石灰、堆肥、ミネラル分少々と肥料を撒いてから水も散布します。これでも40%くらいの定着率でした。なので昨年は、無施肥で苗木を植え付けたました。驚くことにその結果は、100%近い定着率であった事を付け加えます。
.jpg) |
| デラウェア 自然栽培 植え付け |
雑草は、大事
また雑草についての事を追記します。今までは除草剤を使わず草刈り機で除草をしていました。「雑草を放置しておくと、せっかく施肥した養分を雑草が吸い取ってしまうので、できるだけきれいに除草をする」というのが小学校で習った長年の常識です。なのでしつこい雑草をきれいに春から月に2回以上は、草刈りを実施していました。これは、正直たいへんな仕事量でした。今まではきれいに刈り取っていましたが、一週間すると雑草の生命力はすごいです、以前よりすごい勢いでまた生えてきます。昨年は、無農薬で「奇跡のリンゴ」等の自然栽培を参考に雑草も刈らない方針で進めました。「春草」を刈らないでいると「夏草」があまり生えてきません。それでも「夏草」は結構な勢いで生えますので、作業の邪魔になってきます。そうすると腰の高さまで生えてきてから生え際から10cmを残して雑な草刈りをします。期間中1回の草刈りで済みました。以前は、シーズン中10回くらいは実施していたと思います。それも全部の圃場ですから、相当な労働力の負担でした。夏場は、頭がクラクラします。これは、私の私見でエビデンスもないですが、葡萄の病気も草刈りが原因でなるものもあるような気がしてます。草刈りはしなくていいのです。必要最低限の草刈りでいいのです。天候がよかったせいもあるのでしょうが、昨年は病気の発生は、ハウス栽培ではなかったです。ただ昆虫は多かったです。すごく自然豊かな圃場でした。蝶は飛び交い、蜂はブンブン、ですが、虫に害を受けたものは殆ど見受けませんでした。クサ虫(カメ虫)は、多かったです。葡萄の房に隠れているカメムシが時々梱包にまざって混入していたものがあり、お客様からクレームがありました。なので言い訳ではないのですが、「無農薬ですので、時々虫、蜘蛛の巣が混入しているときがあります」とのアナウンスをし、注意喚起のビラ、HPへの記載をする事にしていました。それが原因で、農林省のこわい有機JAS査察官が来られたて厳しい検査を受けたわけです。
緑肥もいいという話がありますので、これもいろいろな種を撒いています。
 |
| うちのデラウェアハウス 雑草ぼうぼうです。 |
昨年の成果と問題点
昨年の収穫の成果は上々でした。特にデラウェアその他の糖度が高かったのが驚きです。お客様からは「お宅の葡萄は甘くて、スーパーの葡萄はもう食べれない、また買いに来ました」とまで言っていただきリピートで購入していただいた方もたくさんおられました。糖度は、最高のもので29度を記録しました。
糖度計:29度
ただ、問題もあります。ハウス栽培のデラウェアは、上々でしたが、やはり露地栽培のデラウェアは、不調でした。私が農地を父から遺産相続した当初は、化成肥料を使用していましたが、その後有機肥料に移行し、ハウスのほうは問題なく切り替わりましたが、露地が、収穫前までは、立派に育つのですが、色づき始めると毎年腐ります。そんな事がもう10年近く続いています。バンプ病だそうです。一昨年は、バンプ病の農薬を2回散布しましたが、やはり腐りました。でも、近所の慣行農業で露地のブドウ栽培をされているところは、昨年もりっぱなデラウェアを栽培されていました。最初の頃は、天候のせいだと思っていました。有機肥料に切り替えた当初、日本中が悪天候で、雨が多い年で各地で災害級の大雨でした。何が原因なのか指導員に質問してもベテランの農家に聞いていろいろ対策もしましたが、まだ解決に至っていません。化成肥料を10年位前までずっと使っていたので、土壌の微生物が回復するまでにやはり長年かかるという事なのでしょうか。それとも他に原因が?でも私が農地を父親から相続して2,3年は、まだ化成肥料でしたが、りっぱな葡萄が収穫できていたのも事実です。
理論的な裏付け
まず、作物にとっての栄養素、窒素、リン、カリが必要なのは、小学校の理科で習う常識で大体義務教育を受けている人はわかります。「無施肥でどうして農作物が育つの?」という疑問が浮かびます。私も最初にそう思いましたので、いろいろ調べてみる事にしました。
ここまでわかった自然農法、
書籍に記述されているように空気中から窒素を微生物が植物の吸収できる形に固定化し、鉱物資源であるリン、カリは、土中からまた微生物が植物の吸収できる形にするという事です。なので土壌中の微生物が重要な鍵となるという事です。マメ科の植物の多くは、根粒菌と共生し、空気中の窒素をアンモニアに変える能力があります。この、空気中の窒素を動植物が利用できる形態に変換することを窒素固定と呼び、窒素固定をおこなう植物はヤシャブシの仲間や、ヤマモモなども挙げられますが、代表はマメ科植物です。膨大なエネルギーを消費するハーバーボッシュ法による窒素固定とは、違い驚くべき省エネな窒素固定方法です。
<シロツメクサの根粒>
また、
BLOF理論というものも4年前から実践しています。有機栽培ですが、各圃場の土壌分析を行った結果のデータを元に施肥設計をし、その計算結果をもとに施肥を実施します。なので昨年は有機肥料の施肥を実施して無農薬でしたが、完全な自然栽培では、ないですが、今年の栽培は、足らないミネラルと酸性堆肥少々の礼肥のみで窒素分を大幅に削減しました。いきなり無施肥で栽培というのもリスクが多すぎるので、今年はまずこれで、少しづつ無施肥を実現していきます。以下の図は、ここ4年間の土壌分析したデータをグラフ化したものです。雑草を刈らなかった昨年は、リン酸、カリが増加している事がわかります。これは、1個の圃場の例ですが、他の圃場もだいたいこの傾向がありました。
<BLOF理論による土壌検査>
 |
| 4年間の土壌検査結果 |
可能性の実感
問題点もまだ多くありますが、自然農法の可能性を実感しています。そして完全に今までの常識や固定概念を否定された年でもありました。また、昨年は、無農薬という事で販売したおかげで、興味を持ってくれるお客様が多くその中である人が紹介してくれた「むちゃくちゃおいしい野菜が採れる」という微生物資材があるという話で、これも礼肥を施肥した際に露地のデラ圃場等で一部試しています。現在、いろいろな微生物資材が発売されているようです。慣行農業から、自然農法に移行するには、けっこう苦労すると言われている中、こういったもので、短期間に移行できる事ができれば、今後もっと自然栽培(有機栽培)等が、注目され、移行する農家が増えるのではと思っています。木村秋則さんでも10年かかられたようです。これはすごい努力と忍耐が必要ですが、なんとかそういう時間も短縮できれば農業に将来が見えてくるのではないかと今考えています。
最後に、今更、産業革命以前の時代や縄文時代の農業に戻ろうとは思いませんし、そうしましょうと言っているわけではありません。我々は現代の科学技術の恩恵を担っています。しかし特に農業は、特にIT化の恩恵を全く受けていないと言えるのではないでしょうか。零細農家はほとんど「IT化(スマート農業)なんて無駄な投資だ。」と思っています。それは、現在のスマート農業の進め方が間違っているためです。一部の大きな農家だけが少しは恩恵を受けているかもしれませんが、家族で農業を営んでいる昔ながらの農家が、恩恵を受けるようなIT機器は、メーカーが作る気もないようです。儲からないからです。そういうところに公的な援助がされるべきだと私は思います。農業のIT化やスマート農業は、つまるところ、小規模の農家にも開放される必要があります。大規模の農家だけでなく、家族経営の小規模農業にも有用なツールやサービスの開発が望まれます。このため、公的な援助やサポートの実施が必要です。
ですが、誤解を受けないように付け加えます。ビルゲーツの提唱するデジタル農業は、大反対です。私が考えるのは、小規模農家でも使える統合型スマート農業ツールです。
安価なIoT機器を利用したハウスのモニター(コントロール)装置を開発中です。別の機会でまた紹介します。
マイクロソフトの創業者であるビルゲイツ氏は、莫大な資産を元に地球上の土地、特に米国の農地を買いまくっているようです。大規模農業をIT、AIで効率よく経営してまだまだ精力的に事業を拡大しようとしています。もうITでの限界を感じているのでしょうか?農業に目を向けること自体確かにさすがにするどい洞察力を持った経営者であるとは思いますが、基本的な考え方が誤りです。AIに農業の経営を判断させて人間(安い移民の作業者)に労働をしいて進めるやり方は、AIの間違った進歩を促します。また、
スマートグラスという眼鏡をつけさせAIの判断で人間に仕事をさせるという方式は、根本的に間違っています。人間をアクチュエーターにするなんてもっての他です。AIの指示で人間が動くというのは、人間の進化を阻害します。センサーから得たデータを元にアクチュエーター(ロボット)が仕事をするならばわかります。基本的な考え方が間違っているように思います。農林省は、スマート農業実証事業といってこういう研究を採択していますが、何も農業の事を理解されていないです。その昔、あほな経産省は、日本の優れた国産OSである坂村先生が作ったTRONをWINDOWSに貿易摩擦だという世論をマスゴミにあおらせ、明け渡してしまいました。その結果WINDOWSが世界標準になってしまったのですが、今やTRON-OSはIoTの世界で最も活躍しているOSとなっています。
農業は、ITの恩恵を最も受けていない産業だと思います。さらにいうと大規模農業にしか活用方法を見いだせていないです。小規模農家でも活用できるスマート機器を開発して有効活用し、農業経営の発展に寄与すべきです。ビルゲイツ氏は、農業を実際にした事があるのか更に農林省の役人が実際に農業を経験したことがあるのか、はなはだ疑問です。農業の事を全く理解しないでただただ金儲けの手段としてのみ考えているので、農業基本法の改悪とかスマートグラスとか全く意味不明な事ばかり進めているのでしょうね。「今だけ、金だけ、自分だけ」(鈴木宣弘氏の名言)では、だめです。
正しい農業こそが、地球環境を救ってくれるものだと信じています。そうならないとこの地球は日本は、本当に終わってしまいます。もうカウントダウンの時かもしれません。農薬が全て悪いとは思いません。必要な農薬、安全な農薬はあるはずです。そういう最新技術の活用もし、IT技術の活用もし、今後の農業を支えていくべきだと私は考えます。農業政策とエネルギー政策が重要です。これらが日本防衛の基本です。今後の日本の将来、我々の子孫のために正しい行政をしてほしいものです。
世界で最初に飢えるのは残念ながら日本です。

.jpg)